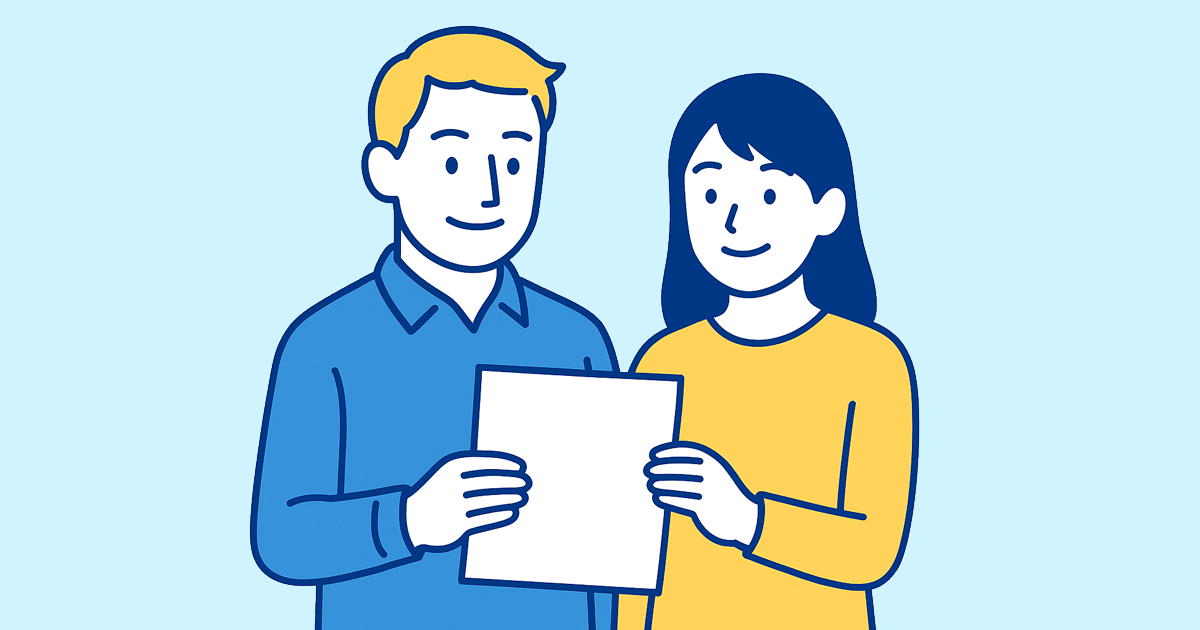
国際結婚が増えている今、相続においても外国籍の配偶者が関わるケースが増えています。日本国内での相続手続きにおいては、国籍や居住地によって必要書類や流れが異なることも。今回は、外国人配偶者が相続人になる場合の基本的な考え方と注意点を解説します。
1. 外国籍でも日本の相続法が適用される?
原則として、相続は「被相続人の本国法」によって処理されます。つまり、日本人が亡くなった場合は、日本の民法に基づいて相続の手続きが行われます。配偶者が外国籍であっても、日本での財産については日本の法律に基づいて相続が進むのが基本です。
2. 相続人としての資格と権利
外国籍の配偶者も、日本の民法上では「配偶者」として法定相続人になります。相続分も日本人配偶者と同じように認められます。ただし、各国の法律や条約により、相続に関する追加手続きが必要な場合もあるため、注意が必要です。
3. 書類の準備と翻訳
外国人配偶者が相続人になる場合、次のような書類が必要になることがあります。
- 出生証明書・婚姻証明書(本国発行)
- パスポートや在留カードなどの身分証明書
- 書類の日本語訳(翻訳者の署名が求められる場合あり)
これらの書類が日本の役所で受理されるためには、アポスティーユや領事認証などの手続きが必要になることもあります。国によって大きく異なるため、事前確認が重要です。
4. 海外に住んでいる場合の実務上の注意点
相続人が海外在住の場合、遺産分割協議書への署名・押印のために在外公館(日本大使館・領事館)での手続きが必要になる場合があります。郵送や時間差、印鑑証明に代わる制度など、国内の相続手続きとは異なる点も多く、時間と手間がかかります。
専門家によるサポートが安心
国際相続は、通常の相続と比べて確認事項・必要書類が増える分、手続きの難易度も上がります。行政書士や弁護士といった専門家に早めに相談することで、トラブルや手戻りを未然に防ぐことができます。

コメントを残す